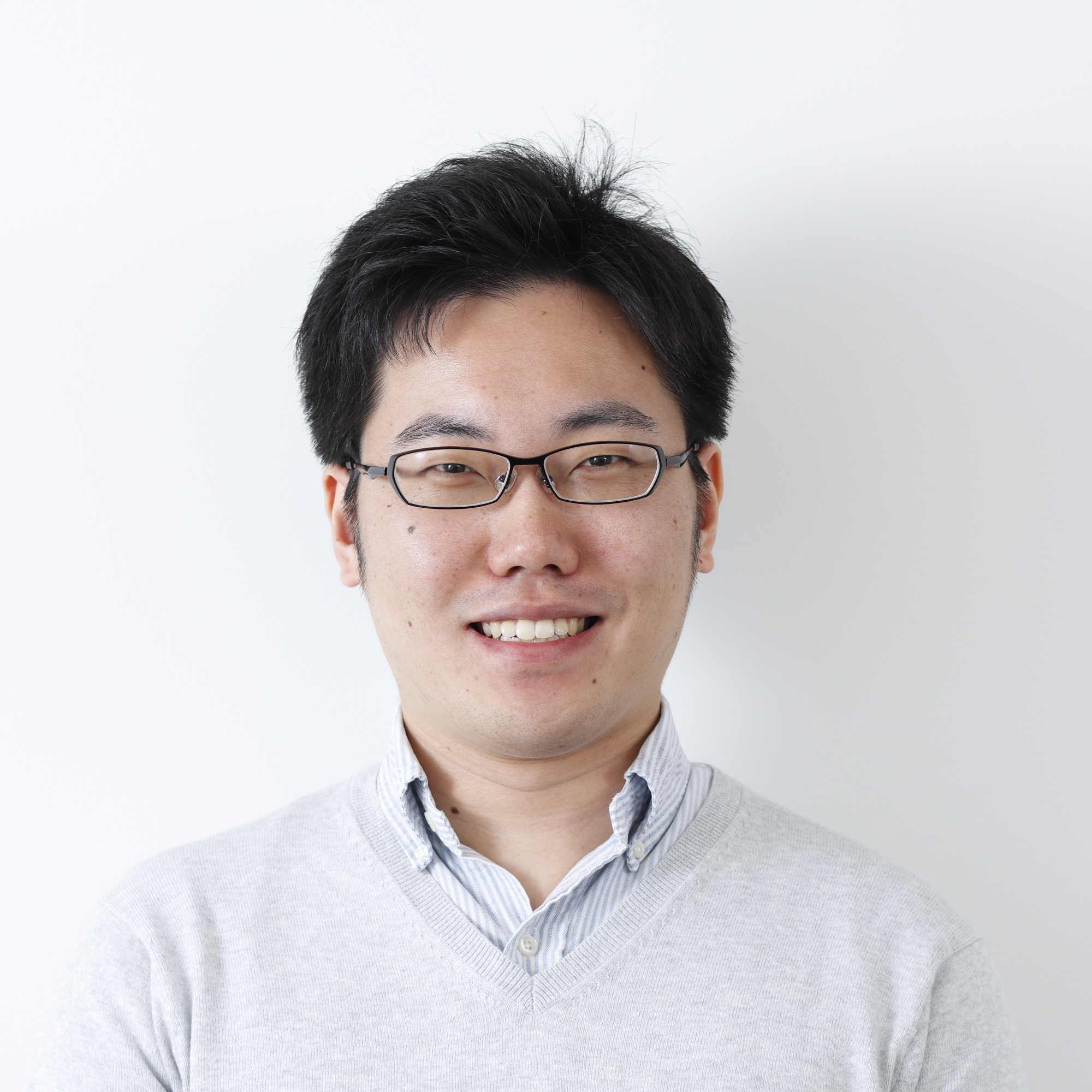reports
【2023 年末】自分のまわりで感じる IT トレンドの 9 のテーマ
2023 年ももう終わろうとしています。 この 1 年、私が身のまわりで感じた IT トレンドについてまとめようと思います。 機械学習関連とその他、という大きく 2 種類でまとめていきます。
Read【2022 年末】自分のまわりで感じる IT トレンドの 13 のテーマ
2022 年ももう終わろうとしています。 この 1 年、私が身のまわりで感じた IT トレンドについてまとめようと思います。
ReadECS on Fargate のデプロイツールを調べてみた【ver2022】
ECS on Fargate は AWS のアプリケーション実行環境として近年定番の選択肢です。 そんな ECS on Fargate について、Infrastructure as Code や CI/CD などを含めて環境を整えようとすると、何かしらのツールが必要になります。 2022 年 12 月の時点で ECS on Fargate のデプロイツールをいくつか試してみたので、得られた知見をまとめておきます。
ReadNode.js のサーキットブレーカ opossum をさわってみた
マイクロサービスなどで利用されるサーキットブレーカと言えば、最近は Envoy (Istio) が最も有名です。 Envoy は別プロセスのプロキシ (コンテナのサイドカー) として導入してサーキットブレーカとして利用可能ですが、サーキットブレーカには各種言語のライブラリとして導入可能なものもあります。 Node.js ライブラリ形式のサーキットブレーカである opossum をさわってみたので、その概要や感想をまとめます。
Read【2021 年末】自分のまわりで感じる IT トレンドの 8 のテーマ
2021 年ももう終わろうとしています。 この 1 年、私が身のまわりで感じた IT トレンドについてまとめようと思います。
Read【予算 10 万】PC を自作するにあたって考えたこと【2021 年】
私は普段 MacBook を使っており、Linux などが使いたければ AWS などでインスタンスを立てていました。 そんな中、VR 系のサービスに興味を持ち、それらを楽しむためには Windows マシンが手元にあった方がいいということが分かりました。 せっかくの機会ということで PC を自作したので、その際に考えたことなどをまとめます。
ReadPuma の Daemonization が廃止された理由と、デーモン化したいときはどうするべきか
「Puma をデーモン化する設定はなぜ廃止されたのか」、「代替手段の puma-daemon によるデーモン化はどのように実現されているのか」を調べたところいろいろ勉強になったので、記事としてまとめます。
ReadAWS App Runner が Ruby のソースコード連携に対応してなくて面倒?そんなときは Cloud Native Buildpacks
先日 AWS に App Runner という新サービスがリリースされました。 コンテナイメージの作成を自動でやってくれる Cloud Native Buildpacks と GitHub Actions を使って、Dockerfile を書かずに App Runner で Ruby のアプリケーションを起動してみようと思います。
ReadAWS App Runner を早速さわってみた【接続数でオートスケーリング・ゼロスケール(?)】
本日 (2021/05/19)、AWS に App Runner というサービスがリリースされました。 App Runner は、コンテナアプリケーションを非常に簡単にデプロイできるサービスのようです。 GitHub と連携した自動デプロイや、接続数でのオートスケーリングを試したのと、ゼロスケールのような挙動に気付いたので、そのあたりをまとめました。
Read